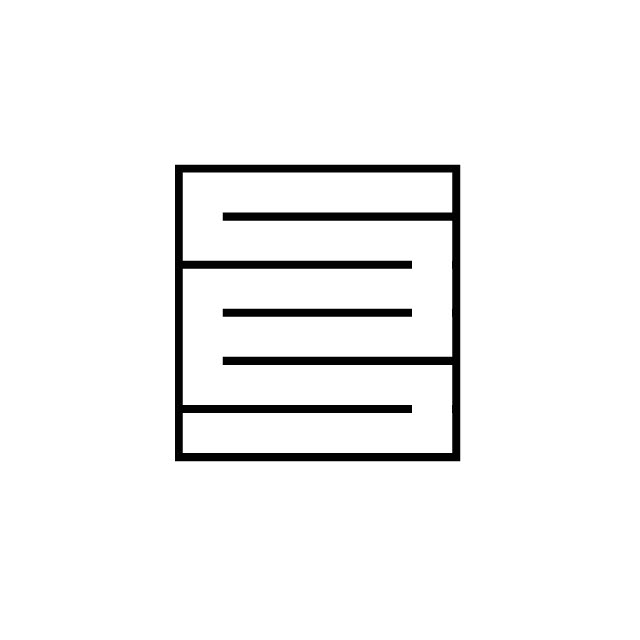「そこで、神だけが原初的な一なるもの、すなわち本源的な単純実体であり、創造されたすなわち派生的であるモナドは、すべてその生産物で、いわば神性の不断の閃光放射(fulgurations)によって刻々そこから生まれてくる。けれどもこの創造されたモナドは、本質上有限な被造物の受容性のために、制限を受けている。」(ライプニッツ『モナドロジー』47 谷川多佳子・岡部英男訳)
イランにおけるネオンカリグラフィーを撮影したシリーズ。イスラーム圏であるペルシアでは伝統的に書道文化が発展してきたが、現在ではその一端を町に灯るネオンにも見出すことができる。ネオンの看板屋が並ぶ通りでは各店がその腕を競い合うように“書”を発光させている。
イスラームにおいて書は「霊魂の幾何学」であり、見えない神的生成の流れを筆(قلم)を通じて「見えるもの」へと結晶化させたものであると言われる。さらに、ある中世ペルシアのスーフィーによると“至高の筆”は光そのものであるという。つまり眼によって知覚しうるもの全てが(神による)カリグラフィーということだ。ここにおいて世界は神的な筆による“photo”「光」“graph”「描かれたもの」の不断の運動というヴィジョンが到来する。闇夜を疾駆する光の筆の運動。それは闇を引き裂き、神的生成の光子を放電させる、速度であり、線分であり、痕跡の結晶なのである。